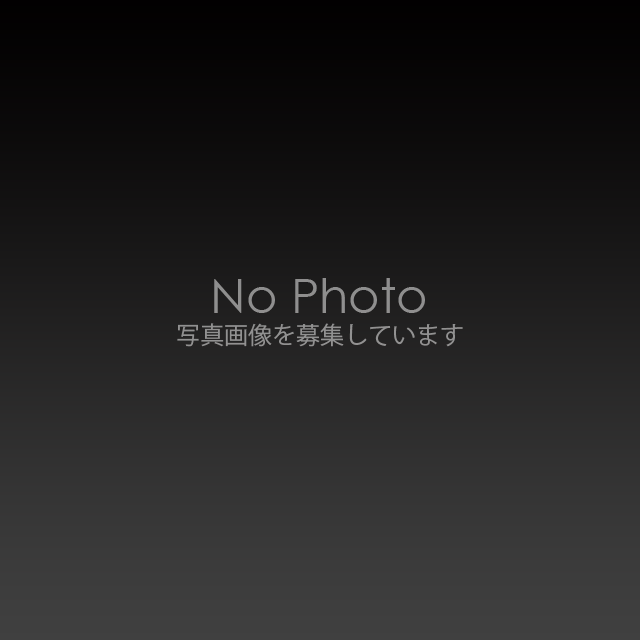東大寺は、「奈良の大仏」として有名な盧舎那仏(るしゃなぶつ)を本尊とするお寺です。別名、金光明四天王護国之寺とも呼ばれています。
728年、聖武天皇が皇太子を供養するために建立した金鍾山寺(きんしょうさんじ)が東大寺の始まりです。741年に「各国に国分寺と国分尼寺を建立するように」との天皇からの勅令が発せられると、金鍾山寺は大和国の国分寺として金光明寺と呼ばれるようになりました。752年に盧舎那仏の開眼供養会が催された後、西塔・東塔・講堂などの造営が進み、少しずつ東大寺としての形が整っていきました。
東大寺の完成後は天災や火災などの影響で、修復を繰り返しています。現在の伽藍は1709年に再建されたものです。盧舎那仏を安置する大仏殿も何度か失われ、1567年の三好・松永の兵火では焼失してしまいました。三好・松永の兵火の後は仮殿が作られましたが、その仮殿も強風で倒れ、奈良の大仏は100年近く風雨にさらされていたと伝わっています。
東大寺の有名な行事は、毎年3月に行われる「お水取り・お松明」。2月の後半から始まる前行と合わせると、約1カ月にも及ぶ大規模な法会です。752年に始まってから、1200回以上1度も途絶えることなく続いている伝統行事です。



 東大寺のイベント情報
東大寺のイベント情報